税金・医療費が家計圧迫=全婦協実態調査
「大好きな商売を続けたい」―。全商連婦人部協議会(全婦協)が昨年12月にまとめた「2012年全国業者婦人実態調査アンケート」には、9879人が回答を寄せました。自営業に携わる業者婦人を対象に行った全国調査は、営業上の困難さや生活費に食い込む税制度、福祉政策の矛盾を浮き彫りにしています。6回連載予定で解説します。(2回税金、3回社会保障、4回健康、5回経営、6回女性事業主)
福祉施策の貧弱さ反映
大企業が、人件費を減らし雇用を切り捨て、不況をいっそう深刻化させているもとで中小業者の経営と暮らしはさらに困難さが増しています。
売り上げ状況を所得階層別に見ると、低所得層で大幅に減少。所得200万円未満では、売り上げが前年より「半減した」と回答した人の割合が44.7%。また、所得1000万円超の高所得層でも2割超が赤字と答えています。
家計を圧迫しているものについて、上位を占めているのは「各種税金」(55.7%)、「国保・年金」(48.1%)、「借金返済」(25.8%)、「医療費」(18.2%)「生命保険等」(16.1%)など、度重なる庶民増税と社会保障切り捨て政策が家計を直撃しています。
所得別の特徴としては、低所得層では2割以上が「医療費」、中所得層では5割超が「国保・年金」、高所得層では、6割以上が「税金」の負担感が高いとしています。
体が資本の中小業者に対する福祉施策の貧弱さを反映し、自分や家族の病気が「生活での困りごと」の上位を占めています。
貧困を生み出す政策の転換と個人経営を応援する施策充実が求められます。
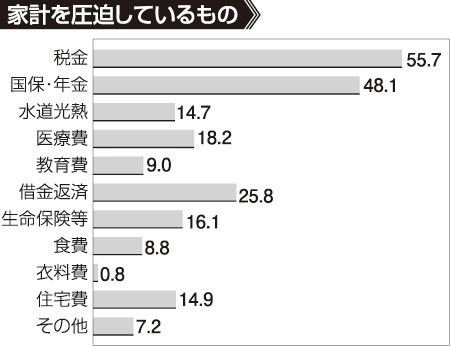
政治の矛盾が明らか リアルな現状示す
2012年全国業者婦人実態調査アンケートは、業者婦人の営業と暮らしの実態を明らかにすることを目的に、売り上げ・所得や税金、資金繰り、健康に関する問題などを調査したものです(実施期間は2012年4月〜6月)。
その結果は、経営の困難さと暮らし・健康が密接不可分な関係にあること、その原因に税制・福祉政策などの問題があることを示し、運動を進める上でも貴重なものとなっています。
回答を寄せたのは、事業主を支える家族従業者と女性事業主で家族従業者の割合は58.6%と過半数を占めています。また、建設、製造、卸・小売、サービス、料理・飲食などの多岐にわたる業種から回答を得ており、地域は、全国47都道府県を網羅しています。
13回目となる今回の調査では、東日本大震災の影響や金融円滑化法による条件変更についても調査しています。
また、年代別集計では世代間の経営意識の違いなどについても明らかにしています。
老後や子どもの将来不安 一言欄から
●新潟・料理飲食(50代)
ラーメン店を夫婦2人で経営、主人の医療費が月に1〜2万円かかっている。発達障害の24歳の子どももいて、これから先、もし主人が倒れたら私1人では、ラーメンは作れない。
●埼玉・建設関連(60代)
不況の上に震災後の仮設住宅の建設で労働力を東北にとられ、材料不足もあり県内の建設業は大変。消費税が払えず、延滞税がかさみ、材料の保証金を差し押さえられ、メーカーとの長い信頼関係に影響をもたらしてしまった。
●長野・卸小売(39歳以下)
リーマンショック以降、売り上げはますます減り続けている。自分の努力や工夫はもちろんだが、これから先子どもたちの教育費や自分の老後のことを考えると不安。それはそのまま国に対する不心感にもつながる。政治家は自分たちのことしか考えていない。
●福島・建設(50代)
国保税、国民年金が高く、支払いが滞っている。分納しているが将来が心配。夫は腕を痛め、長く仕事が続けられるか不安。
全国商工新聞(2013年1月14日付) |