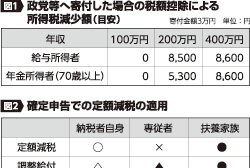阪神・淡路大震災から丸30年。大きな被害に見舞われた神戸市内を歩くと新しいビルが立ち並び、”復興”したように見えますが、生業の再建や借り入れ返済に苦しむ業者が、今も残されています。毎年のように自然災害が起きる今日、何を学ぶべきなのか―。商売と運動に励んできた民主商工会(民商)会員に、これまでの歩みと今を聞きました。
公的支援の整備急げ 被災者の声出発点 兵庫県連会長 土谷洋男さん=印刷

私が尼崎民商の会長になって半年たった頃、大震災が発生しました。
全てが手探りでしたが、被災した会員や地域住民を訪問して要望を聞いて回り、国や自治体に要請しました。
その結果、被災者以外にも対象者を広げた災害融資制度が創設され、「被災者の声が復興の出発点や」と実感しました。民商と県連(兵庫県商工団体連合会)が「神戸空港など”ハコモノ復興”ではなく、被災者にお金を使え」と、直接補償を求めて運動したことが、東日本大震災での「グループ補助金」創設に結び付きました。
この30年、被災した中小業者の多くは借金の重圧に苦しみながら商売してきました。返済を続けながら亡くなった方もいますし、今も返済に苦しんでいる方も残されています。
能登半島地震の状況を見ても、被災者への公的支援制度がまだまだ整備されていないと感じます。引き続き、政府に役割を果たさせていく運動が必要です。
阪神・淡路大震災

1995年1月17日午前5時46分、兵庫県南部の淡路島を震源地として「1995年兵庫県南部地震」が発生。淡路島や阪神地区では、観測史上初めてとなる震度7を記録する激震となりました。
広範囲にわたり道路や鉄道、電気、ガス、水道などのライフラインが寸断され、31万6678人が避難(同年1月23日時点)。死者6434人、負傷者4万3792人、63万9686棟の住宅被害を出しました。
全国商工団体連合会(全商連)は直ちに「対策本部」を設置。大阪をはじめ全国の組織が募金や救援物資搬送などに奮闘しました。兵庫県内の民商と県連は、震災直後から被災中小業者の相談活動に奔走するとともに、労働組合などと「救援・復興県民会議」を結成。被災者への公的支援拡充・個人補償実現の運動を展開し、98年5月に「被災者生活再建支援法」を成立させる契機となりました。

復興の在り方考える中小業者も登壇し発言各地で記念行事


30年の区切りを迎えた1月17日、兵庫県主催の追悼式典や各地域ごとの記念行事が行われました。
神戸市全体の住宅焼失棟数の7割近くを占めた長田区では午前、「震災復興長田の会」が主催する「つどい」に125人が参加しました。再開発で様変わりした大正筋商店街や、かつて町工場が密集していた一帯などを視察した後、集会を開催。10年前までクリーニング業を営み、長田民商会員でもあった関正人さんが「古くからの商店街がビル街に変わり、シャッターが下りたままの商店が増えた。ケミカルシューズ産業や町工場も衰退。復興が成功したと言えるのか」と訴えました。
午後には、ピフレホール(長田区)で、兵庫県連も加入する「救援・復興兵庫県民会議」が「30年メモリアル集会」を開催しました。講演では「被災地には、学ぶ責務と、伝える責務がある。大震災の経験を大いに語っていこう」(室崎益輝・神戸大学名誉教授)、「(能登半島地震の状況を踏まえ)元の場所に住み続けたいとの当たり前の要求や、どこに住むかの自己決定権は、憲法で保障されている」(井上英夫・金沢大学名誉教授)と強調。「人間の尊厳ある暮らし」の再建をめざす決意を固め合いました。

 03-3987-4391
03-3987-4391