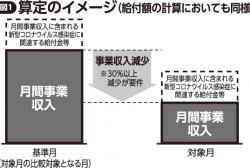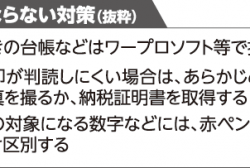税務署の拡大解釈に歯止めなくなる恐れ
今年から、前々年(2020年)に300万円超(前号の「以上」は「超」の誤り)の収入金額がある雑所得者の記帳義務が規定されている。それが定着していないうち(この改正は来年から通用される)に、罰則に等しい規定を設けるのは乱暴であろう。
国側の説明に法的根拠ない
国側の「刑事告発するような大きな事案が対象」という説明も、条文上の根拠がない以上、将来の保証は全くない。というのも、この「刑事告発するような事案が対象」のはずが広がっている例がある。
「偽りその他不正の行為」があれば、時効が2年延び、7年分の課税が迫られる(国税通則法70条5項)。しかし「偽りその他不正の行為」がある場合には、刑事罰が科される旨が規定されている(法人税法159条、所得税法238条)ことから、この7年分の課税処分は、刑事罰が科されるような悪質な事案だけのはずである。
しかし昨今は、隠蔽仮装として重加算税が付加されれば、同様の事実を基に、「偽りその他不正の行為」があったとして7年分の課税処分が行われている。言葉の範囲としては隠蔽仮装よりも「偽りその他不正の行為」の方が広いが、そのほとんどに刑事罰は科されていない。これなど刑事罰を科すような事案だけのはずのものが、そうでなくなってきている例である。
また税務調査において、本来は隠蔽仮装には当たらないにもかかわらず、隠蔽仮装とされた例が多くある。国税不服審判所から公表されている裁決事例集にも、隠蔽仮装として賦課された重加算税の取り消し例が、ここ数年複数公開されている。隠蔽仮装でないものを隠蔽仮装だとして経費否認される例が起きそうである。例えば、帳簿の誤記入について、ミスにもかかわらず、故意として隠蔽仮装とされそうである。収入とそれに関する費用の計上漏れがあったときに、それが税務調査で発覚すれば、収入のみを加算されることになりかねない。
隠蔽仮装とされて経費算入を否認された上に7年分の課税がなされ、加算税(今回の改正では記帳がない場合の加算税も増額されている)や重加算税まで課されれば破産するしかないであろう。
立法時の制約守らない例も
なお税法の解釈には、侵害法規性があることから、立法趣旨ではなく、条文の文言が優先される。その結果、立法当時に課された制約が忘れ去られている例が多くある。
第2次納税義務を定めた国税徴収法39条は「その運用を極めて慎重にすべきことが諒解されている」(租税徴収制度調査会・我妻栄会長)はずであったが、「よく切れる刀を持つ者が必要以上に切らないように自制することは、すこぶる困難」(同会長)と危惧されたように、この39条がさまざまなケースに適用されている。また法令ではないが財産評価基本通達の6項「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する」は、本来は納税者を救済するための規定であったが、昨今は課税処分をするために用いられている。従って、法令上でしっかりした歯止めが必要であろう。

 03-3987-4391
03-3987-4391